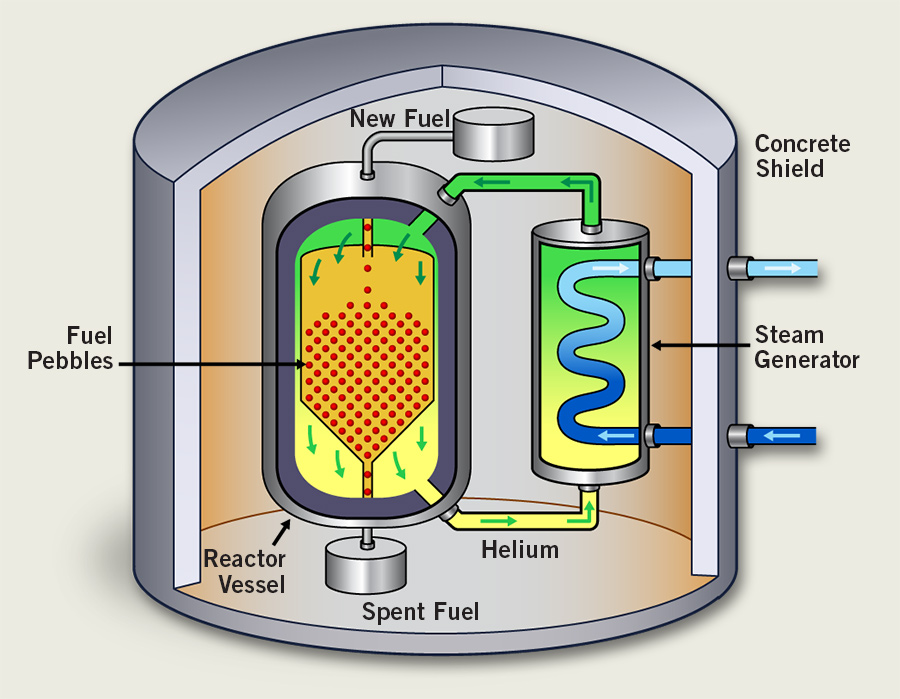米国債は6月、政府債務の上限をめぐって債務不履行(デフォルト)の危機に立たされた。日本経済新聞は「最悪の事態を招いていれば各国が保有する米国債は暴落し、ドルの信用も失墜する瀬戸際だった」と振り返る。
危機は去ったわけではない。債務上限の効力を一時停止した時限立法の効果は2025年1月に切れる。24年秋の大統領選後に発足する米国の新政権は再び、政府債務問題の解決を迫られることになる。
ところで、ここであえて問いたい。国債のデフォルトとは、どんな犠牲を払っても絶対に避けなければならない事態なのだろうか。
あらためて国債のデフォルトとは、政府が国債の利息の支払いを遅延・停止したり、元本の返済ができなくなったり、契約条件を変更したりすることを指す。
「自国通貨建ての国債はデフォルトしない」という主張をよく目にする。「いくらでもお金を刷ることができるから」というのが理由だ。しかし、生産力を上回るペースでお金の量を増やせば物価が上昇する。ハイパーインフレとまではいかなくとも、物価高が市民の我慢の限界に達すれば、それ以上お金を刷り続けるのは政治的に困難になる。
そこで現実味を帯びるのが、デフォルトという選択肢だ。実際に選択するうえで、考えるべきポイントが二つある。
一つは、倫理に反しないかどうかだ。もしこれが民間の個人や法人間の契約なら、借金の利子を払わなかったり、踏み倒したりすることは当然、倫理に反する。もしA氏からお金を借りたB氏が返済しなければ、A氏の正当な財産を奪うことになる。
しかし、政府の場合は違う。政府が国債を売って市民A氏から借りたお金を返すのは、実際には政府自身ではない。政府に税を支払う別の市民C氏だ。ところがC氏は、その返済について同意を求められたことは一度もない。それどころか政府とA氏との契約は、C氏から同意なしに財産を奪うという前提で結ばれたものだ。このように他人の間で勝手に結ばれた契約に、C氏が何らかの義務を負うとは考えにくい。
したがって、国債の元利払いに充てる税の支払いをC氏が拒否し、その結果、国債がデフォルトに陥ったからといって、C氏が倫理的に責められる筋合いはない。
道路や学校など政府の各種「行政サービス」をC氏が利用していても、国債の元利払いへの協力を強制される理由にはならない。一方的に押しつけられた、必ずしも質の良くない「サービス」に対し、政府の言い値どおりの対価を払う合理的な根拠がないからだ。
国債デフォルトを選択するうえで考えるべきもう一つのポイントは、経済的な影響だ。時価ベースの国債発行残高は3月末時点で1080兆円で、このうち日銀が53.3%にあたる576兆円を保有する。次いで保険・年金が21.9%、銀行などの預金取扱機関が8.9%、海外が7.2%となっている。
日銀は事実上、政府の子会社であり、日銀が保有する半分強の国債はデフォルトによって単純に帳消しすることができる。すべて帳消しにした場合、日銀は保有する国債の価値がゼロとなり、政府が救済しない限り、破綻するだろう。
保険・年金、銀行などの国債保有額は日銀に比べれば小さいものの、デフォルトで価値がなくなれば、金融システムに及ぼす衝撃は大きい。金融機関の連鎖倒産もありうる。個人の保有する保険・年金や預金にも損失が生じるだろう。
しかし、こうした厳しい影響の一方で、デフォルトには明るい面もある。まず、少なくとも当面の間、市民が再び国債に投資するような愚かなことはしなくなるだろうから、政府は借金に頼れなくなり、無駄遣いが減る。日銀が再建されても、以前のような財政ファイナンス(財政赤字の穴埋め)が認められるとは考えにくい。福祉政策や公共事業など粗悪な「行政サービス」は、質が高くて低価格な民間サービスに置き換わるだろう。
また、国債の元利払いがなくなることで納税者の負担が減り、貯蓄を増やしやすくなる。これは資本の充実と生産性の向上につながり、所得回復を後押しする。保険・年金や預金を通じて強制的に購入させられた国債でこうむった損害は、国有財産の売却や民営化株の交付で賠償すればいい。一方、国家を破産に追いやった政府や日銀の歴代幹部は当然、それなりの責任を問われる。
過激すぎてついていけないと思っただろうか。もしかすると今の延長線上で、国民から税金やインフレ税を取り立てながら、破綻を先延ばしできるかもしれない。だが、税収以上に乱費する政府の無責任な姿勢が改まらない限り、いずれデフォルトは避けられない。それならば、少しでも早いほうが痛みは比較的小さくて済む。
<参考資料>