ギリシャでは紀元前5世紀、ペルシャ戦争に勝利を収めると、アテネがほかのポリス(都市国家)を率いる強国へと発展した。このアテネの発展を支えた政治体制が、民主制である。民主制のもとでポリスの市民は、家柄や財産にかかわらず、能力さえあれば誰でも国政に参加して有力者となることができた。その能力とは、多くの人を説得できる弁論術であった。
このようななかで、ソフィストと呼ばれる職業的な教師たちが出現してきた。ソフィストは、報酬を得る見返りに「徳」を教えることを約束した。「徳」とは、ソフィストの場合、国家の中心人物となるための弁論と説得の能力のことだった。
現代では、ソフィストは「詭弁家」という、良くない意味の言葉として使われている。これは古代ギリシャのソフィストが、雄弁術にたけ、詭弁を弄することが多かったからだといわれる。しかし近年、ソフィストをそのように一方的におとしめる見方に対しては、異論が唱えられている。
哲学者ソクラテスやその弟子プラトンがアテネにとどまり、祖国に貢献することを信条としたのに対し、ソフィストは活躍の場を求め、また戦火を逃れて、ギリシャ中を旅して回る諸国遍歴の思想家だった。ポリスからポリスへと教えて回るうちに、相対主義(後述)の鋭敏な感覚を養い、歴史上初めて、批判的思考を我が物とすることができたとされる。その国際的な立場のおかげで、「ポリスの狭苦しい枠を脱することができた」と、フランスの古代哲学研究者ジルベール・ロメイエ=デルベ氏は指摘する(『ソフィスト列伝』)。
自由でコスモポリタン的なソフィストの生き方は、国家への奉仕を唱える哲学者からは、根無草として批判された。プラトンの対話篇『プロタゴラス』に登場するソクラテスは、ソフィストを「諸国を行き来しながらいろいろな知識を売り歩く商人たち」にたとえる。そして商人は自分の売り歩く食品のうち、どれが体によくてどれが悪いか知りもせずに、すべての商品をほめるとおとしめ、ソフィストもそれと同じだと非難する。
哲学者プラトンやその弟子アリストテレスが残した立派な著作集や哲学体系に比べると、ソフィストの残された著作はきわめて少ししかない。これはソフィストが「語ること」を売り物にする専門家だったこともあるだろう。しかしそれ以上に、「批判による抑圧」が加えられたことも想像できると西洋古典学者の納富信留氏は述べる(『ソフィストとは誰か?』)。
ソフィストの教えは、国家を尊重する哲学者からみれば、危険で受け入れがたい部分があった。それは裏を返せば、人々の間に、国家という枠組みにとらわれない自由で合理的な考え方を育てるうえで、大きな役割を果たしたといえる。代表的なソフィスト数人について、その具体的な主張をみてみよう。
プロタゴラスは「神々について」という書物を著し、その冒頭で次のように述べた。「神々について私は、あるとも、ないとも、姿形がどのようであるかも、知ることができない。これらの各々を私が知るには障害が多いから。その不明瞭さや、人間の生が短いこと」
この記述のためにプロタゴラスは、「不敬神」の罪で訴えられ、アテネから追放され、その本は回収され、広場で焼却されたという。
神々の存在が肯定されない以上、精神の拠り所として残るのは人間だけだろう。プロタゴラスの思想は必然的に、徹底的な人間中心主義へと進む。「人間は万物の尺度である」と主張し、ものごとの善悪や真偽を決めるのは個々の人間の考え方や感じ方であるという相対主義の立場を鮮明にした。
トラシュマコスは、プラトンの著作『国家』第1巻で法をめぐり、ソクラテスと対決する場面で有名である。トラシュマコスはここで、法は権力の道具だと主張する。
トラシュマコスは続ける。どの国でも、支配階級は自分の利益に合わせて法律を制定する。そのうえで、自分たちの利益になることが正しいのだと被支配者に対して宣言する。そして、もし誰かがこの法律に違反した場合には、法律違反者、不正な犯罪人として処罰するのだ、と。
プラトンが法と道徳を同一視したのに対し、トラシュマコスは法と道徳を相反するものとみた。この鋭い洞察は、以下にみるように、他のソフィストにも共有されている。
ヒッピアスはプラトンの『プロタゴラス』に登場し、人間同士のように「何かと何かが互いに類似しているとき、両者は自然本来の姿においては同族であるといえる」と語った。その一方、「これに対して、法律は人々を支配する暴君であり、自然本来の姿に反するたくさんのことを強要するのだ」と強調した。
アンティフォンは、断片しか残存していない論文で「法によって正しいとされる命令内容の大部分は、自然に対して戦いを挑むために設けられたものである」と主張する。
けれども、法が抑圧を目指して行う戦いは、初めから負けと決まっている戦いである。現代でいえば、政府がさまざまな経済・社会上の規制を強化しても、問題は解決しないどころか、かえって悪化することを思い出せばいいだろう。
そういうわけでアンティフォンは、法が強いる苦痛は自然に反するものとして、道徳の新たな基準を提唱する。すなわち、有用性、生、自由、喜びである。今の言葉でいえば、功利主義ということになるだろう。
アンティフォンはまた、人々の欲求が共通であるがゆえに人間は普遍的なものなのだ、という基礎づけを行うことができた。この観点からみれば、人々は生まれながらにして平等である。貴族と庶民を区別する必要はないし、ギリシャ人から異邦人を差別する必要もない。アンティフォンは自由人と奴隷の区分に抗議した可能性もあるとみられている。
ギリシャに始まった西洋の「哲学」には近年、さまざまな形で根本的な反省が加えられている。普遍的で絶対的真理の追求と信じられていた「哲学」の営みとは、実は人間理性への誤った信仰であり、科学技術の悪用や全体主義の暴力など、人類を不幸へと導く元凶となってしまったのではないか――。
前出の納富氏はそう指摘したうえで、「「哲学とは何か」を問い直すべき現在、その始まりに批判的に関わったソフィストの意義を見きわめることが、私たちに課されている」と述べる。ソフィストの復権が待たれる。
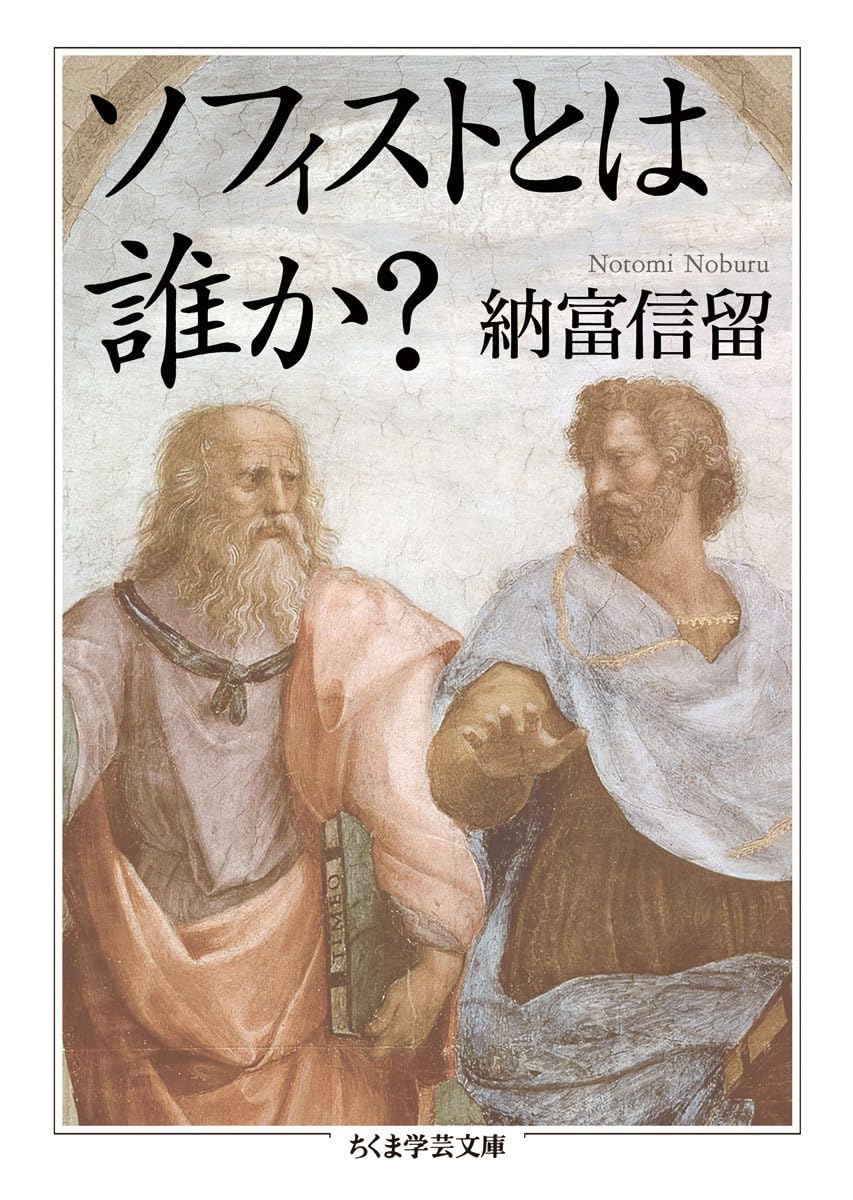
0 件のコメント:
コメントを投稿