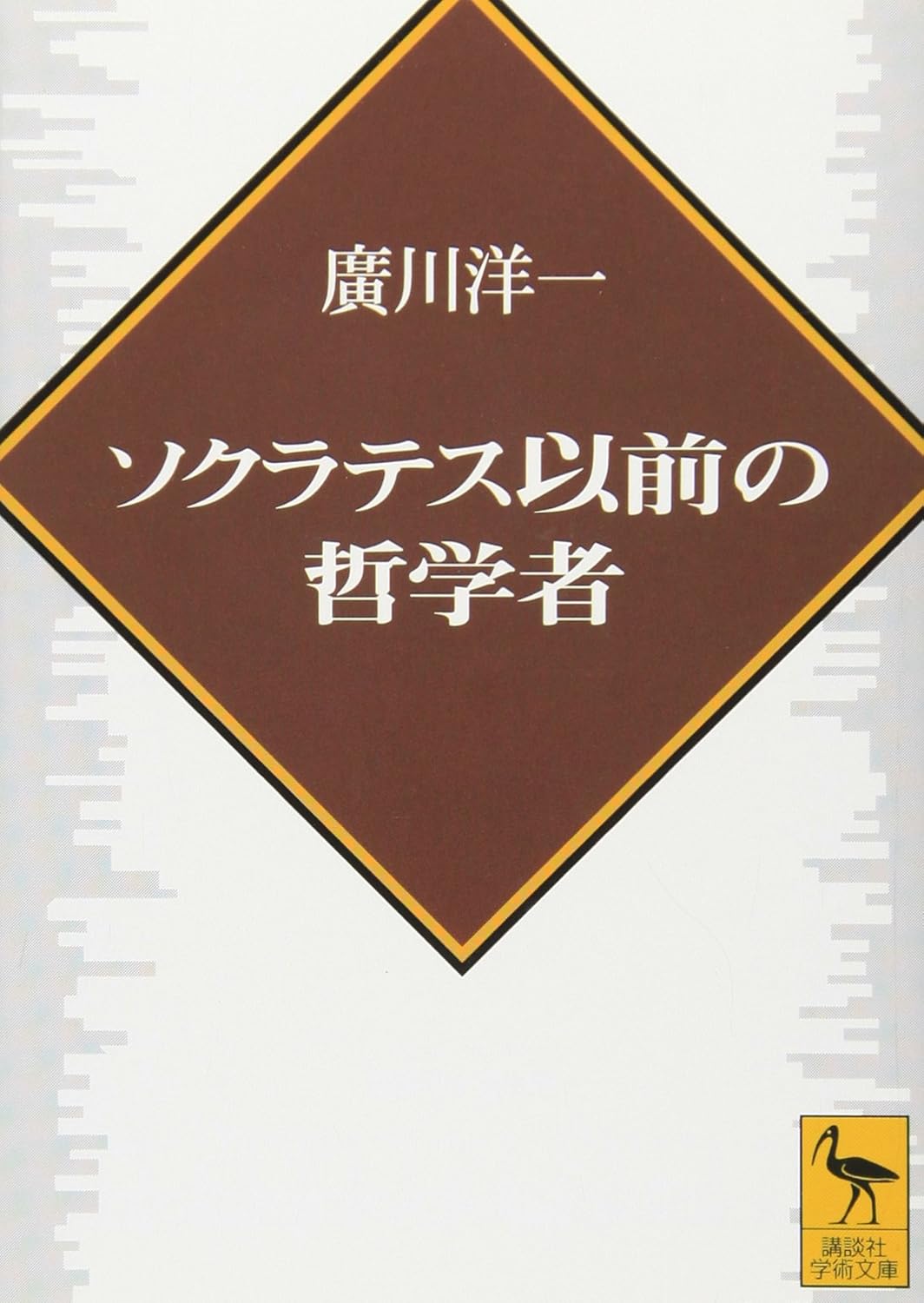ギリシャでは紀元前8世紀に各地にポリス(都市国家)が成立した。ポリスは小規模な共同体であり、市民たちは自らポリスの独立・自治に関与するとともに、自由を重んじた。また、ギリシャ人は地中海沿岸の各地にポリスを建設し、交易を活発に行い、東方のオリエント文化とも接した。
自由な精神や異文化との接触は、やがてそれまでの神話に基づく素朴な世界観や人生観と異なる考え方を芽生えさせることになった。哲学の誕生である。
紀元前6世紀の初頭に、当時の先進的な地域であった小アジア・イオニア地方に新たな考え方をする人々が現れた。初期の哲学者たちである。彼らはとくに自然(ピュシス)を考察した。そのためその哲学は自然哲学と呼ばれる。彼らは神話的世界観を排して、自然の世界は神々の気ままな働きに左右されるものではなく、それ自体で確固とした秩序を備えた存在であると考えた。
そして、その秩序は人間の観察と思考によってとらえられ、さらに、秩序の根拠も人間のロゴス(理性)の働きによって自然そのもののうちに把握されると考えた。世界は人間の理性によって認識されうるとする合理的世界観は、人間を理性的存在とみて、理性を中心にして生きていこうとする理性的人間観と深く関係する。
自然哲学の祖で、哲学の創始者とされるのがタレスである。天文学や数学など多方面で才能を発揮したタレスは、その自然観察をもとに、「万物の根源は水である」と主張した。これを始まりとして、世界の全体について統一的な説明を求める人々が多く現れるようになった。
たとえば、ヘラクレイトスは、万物の原理を火とし、世界の秩序を動的にとらえた。パルメニデスは、「あるもの」はつねに「ある」のだと主張し、「あるもの」がなくなったり、なかったものが「ある」ことになったりする変化や生成消滅を否定するに至った。これに対して、エンペドクレスは、世界全体が4つの元素(火・土、水、空気)から構成され、この4つの元素の混合と分離によって生成や変化が起こると主張した。
これら初期ギリシャ哲学者のうち、経済思想の面から、良い意味と悪い意味で、それぞれとくに興味深い2人にスポットを当てよう。最初はピタゴラスである。
ピタゴラスは前570年頃、小アジア沿岸の島サモスに生まれた。前530年頃、ポリュクラテスの僭主政を避けて、イタリア南部のクロトンに落ち着き、学問性と宗教性をあわせもった一種の結社を設立し、政治的にも大きな影響力をもった。その地に20年ほどとどまったが、政治的動乱のため同じ南イタリアのメタポンティオンに逃れ、その地で没した。
ピタゴラスは、宇宙の調和と秩序の根源を数であると考えた。たとえば、
テトラクテュスはピタゴラスの考えを象徴する図で、ピタゴラス派のシンボルマークだった。1つ、2つ、3つ、4つの点を三角形に並べた図で、4つの数の和は10となり、大宇宙と小宇宙に共通する世界秩序(コスモス)を表す。ピタゴラス教団では、この図形の前で誓いを立てたと伝えられている。ピタゴラスによれば、世界が数であるだけでなく、それぞれの数が道徳的な特質やその他の観念を体現している。たとえば、正義は4であるという。
ピタゴラスがギリシャにおける数学の発展に貢献したことは確かだが、数字そのものに神秘的な意味を持たせるその数秘学には、ついていけないのが正直なところだろう。自由意志をもった人間の行動が織りなす経済現象を、まるで自然現象のように数字だけで分析しようとする、現代の数理経済学や計量経済学の過ちは、ピタゴラスに発するとの見方もある。経済学者マレー・ロスバードがいうように、ピタゴラスは、哲学と経済思想の発展に不毛な行き詰まりをもたらした。
一方、初期ギリシャ哲学者のもう1人の興味深い人物は、哲学と経済思想に前進をもたらした。デモクリトスである。
デモクリトスはギリシャ北方、トラキア地方アブデラの出身。生年は前470年頃で、有名な哲学者ソクラテスとは同時代だが、交流はなかった。レウキッポスという人から原子論を学んだというが、はっきりしたことはわからない。古代における優れた文章家の一人とされ、残された断片から「簡潔で引き締まった、しかも気品のある文体をかいま見ることができる」(廣川洋一『
ソクラテス以前の哲学者』)といわれる。
デモクリトスは、それ以上分割することができない原子と空虚から宇宙全体が構成されていると考え、あらゆる現象は、原子(アトム)の配列と運動によって説明できると説いた。この考えを原子論と呼ぶ。
前出のロスバードによれば、デモクリトスは、経済思想の発展に2つの重要な貢献をした。第1に、近代経済学でいう主観価値説を初めて唱えた。財(商品)の価値は人々が主観的に判断する効用によって決まるという洞察だ。デモクリトスによれば、「善と真は、万人にとって同じだが、快は人それぞれに異なっている」という。この「快」は現代経済学でいう効用にあたる。それぞれの人にどれだけの快、つまり効用を与えるかによって、財の価値は決まる。このことをデモクリトスは「快と不快こそ、有益なものと無益なものを分ける境界線である」と明言している。
2番目の貢献は、私有財産の尊重である。すべての財産を皇帝やその配下の官僚が所有・管理した東洋の専制政治と異なり、ギリシャの社会と経済は私有財産に基礎を置いていた。デモクリトスは、私有財産経済のアテネと集団主義経済のスパルタを比較し、前者のほうが優れていると結論づけた。財産が集団によって所有される場合と異なり、私有財産は勤勉に働くインセンティブ(誘因)を与えると正しく指摘した。
興味深いことに、デモクリトスの原子論は、個人の幸福は快楽を得ることによって実現するという快楽主義を説いたヘレニズム期の哲学者、エピクロスの思想に影響を及ぼした。エピクロスは、人間の生命も原子からなる以上、死を恐れたり不安に思ったりすることは無意味だと考えたのである。
誤解してはならないのは、デモクリトスの快もエピクロスの快楽も、一時的で感覚的な快さではなく、内面的なものであるということだ。デモクリトスが先達となった本来の経済学が前提とする人間は、金銭的利益だけを求める存在ではない。内面的な満足こそ真の快楽であることを知っている。その価値観は初期ギリシャ哲学の合理主義に支えられているのである。
<参考資料>
・廣川洋一『ソクラテス以前の哲学者』(講談社学術文庫)
・It all began, as usual, with the Greeks | Mises Institute [
LINK]